最大震度7の揺れを観測した熊本地震からきょう4月14日で9年です。災害関連死が大きな課題となった地震に、専門家は「避難後も自らの命を守る備えが重要」と話します。
熊本地震では最大震度7の地震が2回発生し、一連の地震で鹿児島県内でも長島町で最大震度5弱を観測しました。災害関連死を含め、熊本・大分両県で278人が亡くなり、4万3000棟以上の住宅が全壊・半壊しました。
熊本市では14日、追悼式が開かれ、遺族らが黙とうを捧げました。
(次女が関連死 宮崎さくらさん)「失ったつらさや悲しみは変わらない。どうしてもあの時に戻りたいと思ってしまう」
地質学が専門の井村隆介准教授です。
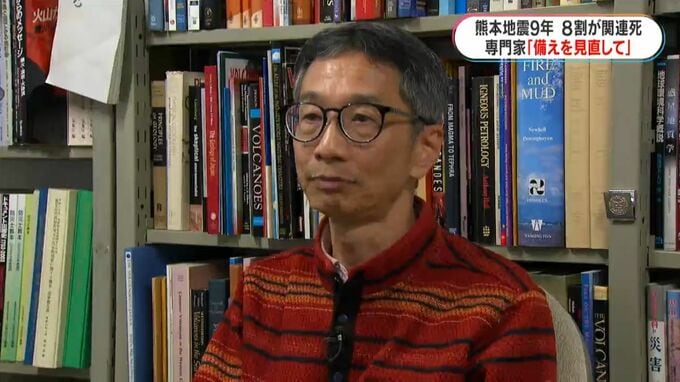
(鹿児島大学・井村隆介准教授)「揺れそのものでは助かった命を、どう次の行動に、本人とまわりが生かしていくのかを突きつけた地震が熊本地震だった」
熊本地震では、持病の悪化や避難生活のストレスなどによる関連死は223人で、亡くなった人のおよそ8割にあたります。
井村准教授は「揺れによる被害から身を守ることが最優先」とした上で、熊本地震の教訓から「避難生活をイメージし、日頃の備えを見直してほしい」と話します。
(鹿児島大学・井村隆介准教授)「揺れた瞬間に、あるいは緊急地震速報が鳴った瞬間にこれが(大きな地震)かもしれないとスイッチがやっぱり入ってほしい。自助という部分を一番大事にしてほしい。避難所生活や災害後の生活に対しても、自助ができていることが共助にまわれる一番大きな条件だと思う」
熊本地震から9年。どこでも起こり得る地震に備え、日頃から考えておくことが大切です。







