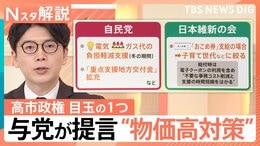妻の首を絞めて殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われている男の裁判員裁判で10日、検察側は懲役4年を求刑した。
公判の中で明らかになったのは実母と妻のW介護の中で疲弊し追いつめられていった男の姿。介護の末の殺人未遂に裁判員たちはどんな量刑を下すのか。
「解放されたい」… なぜ彼は「絞め方」を練習したか
■犯行の瞬間
犯行日となった2025年4月7日。この日も男は妻がたびたびトイレに行くなどしたことで、眠れずに朝を迎えた。そして介護から解放されたいとの思いから突発的に殺害を決意したという。
「(妻や親の介護・家の問題などが)頭にあり、体調と精神面の不調もあって、現状から逃れたい、時間の余裕が欲しい、と思いました」
長女が帰省していた自宅から、妻を実家に連れ出した。母親は入院中で実家には誰もいない。
被告の男「実家の物置でビニール紐を見つけました。トイレから出てきた妻の背後に立ち、無言で首に紐を巻きました」「死ぬかも、というくらいの力で、力いっぱい絞めました」
被告人質問で、男は淡々と、しかし生々しく当時の状況を語っていった。
一度首を絞めたもののうまくいかなかったことから男は脱衣所へ行き、自分の首に紐を巻いて「絞め方」を試した。再び妻のもとへ戻り、さらに強く絞め上げたその時、妻が口から泡を吹き始めたので手を緩めた。
「亡くなったかもしれない……」自分も死のうと思い脱衣所に行って首にひもをかけたがうまくいかない。
すると、廊下で倒れている妻が動くのが見えた。我に返った。「正気に戻ったのだと思います。助けないと、と思いました」。長女に電話をかけさらに自ら119番通報した。
逮捕され拘留された時の気持ちを男はこう語った。
被告の男「正直、解放された」、ホッとした気分でした」
■几帳面、頼れない
長女:「父は『自分が介護しなければならない』と思い込んで、すべてを背負っていました。もともと几帳面な性格で1日の計画をメモして実行するような人間。長男気質で弟妹にも頼れない。介護のために仕事を辞めたため、『自分が家族を支えなければ』と抱え過ぎていたと思う」
大学院卒業後、大手電機メーカーで働いていた男。長女が小学生になるタイミングで独立し技術コーディネーターとしてコンサル業を立ち上げた経歴を持つ。
被告の男:「妻の介護を外部に委託することも勧められましたが、まだやれるという自信がありました。今まで自分に降りかかった問題は自分で解決してきた。まずは自分で何とかしなければいけないと思い込んでいました」
■最終意見陳述で語った「過信」
「犯行に至る経緯に、くむべき事情はない」検察側の求刑は懲役4年。
一方弁護側は「類似の介護殺人未遂25件はすべて執行猶予がついている。妻の認知症の急激な悪化、母親の介護もある中、心と体が追いつめられていたすえの衝動的な犯行。許されるものではないが深く反省している。現在はストレスから解放され更生できる」などとして執行猶予付きの判決を求めた。
公判の最後、裁判官から発言を求められた男は、用意してきた言葉を約5分間にわたり、震える声で読み上げた。
「どんな判決でも受け入れる」法廷で震えた声
「現状と理想のギャップ。それがストレスが極限に達した原因の一つでした。『妻と母の介護は自分でやる』という理想がありました。妻の症状が悪化したことに伴い、自分自身も落ち込んでいき犯行に至った。」
「約2年間母親につきっきりで、夜妻を1人にすることが多く、不安な時間を作ってしまった、これも衆生が進行した理由なのではないかと思う」
「『目標を落とす』ことも一つの選択肢でした。どちらも施設に預けるとか……。自分に対する『過信』がありました。人の意見をちゃんと聞き、客観的に自分を見るべきでした」
「弱い立場の人間を、自分の都合で(手を)かけてしまった。これは否定できない事実です。どんな判決でも、受け入れようと思っています」
現在は保釈され、長女や妹のサポートのもとで生活を立て直している男。入院中の妻の居場所は知らされていない。
妻は自分の身にあったことを全く分かっておらず入院している病院で「お父さん会わないね」と言っているという。
長女:
「事件後、母のメモが見つかったんです。それを見ると3年くらい前からメモを取り始めていた。その頃から認知が始まっていたんだと思います。母はそのことを言えずに苦しんでいたんだと思う」
明快にこたえていた長女は母親のことを語る時、声を詰まらせた。裁判員も目頭を押さえる。
その真面目さゆえに抱え込み、はじけてしまった男の心。
老々介護のW介護、超高齢社会のひずみが事件として浮き上がった今回の犯行にどんな判断が下されるのか?判決は11月17日に言い渡される。