昨今、少子高齢化が進み「お墓ばなれ」「お墓じまい」の関心が高まっている。
中でもお墓じまいについては、子どもに負担をかけたくないという理由から、親が決断するケースが急増しているようだ。しかし、実は子ども側は墓を継ぐことを負担に思っておらず、むしろ前向きに捉えている人が多い。(※注)
現役世代も、お墓参りは心のよりどころとして、大切にしたいという強い思いをもつ人が多いようだ。
こうした中で、セトクラフトでは年配層だけでなく、とくに若い世代の人たちにも、より良いお墓参りを無理なく習慣づけてもらうことを目的に、国内初となる陶器製アイテム「花レンヌ(カレンヌ)」を独自開発し、販売を開始した。
カレンヌのねらい、販売に至った思いについて話を伺ってみた。
※仏事関連総合サービスの株式会社メモリアルアートの大野屋が10代~70代以上の男女500名を対象に「親・子世代におけるお墓の意識調査」を実施。(2021年3月)
子世代= 「親・祖父母がお墓を所有している方」を対象に「祖父母・親の死後、祖父母・親が所有しているお墓をどうしたいか」について聞いたところ、お墓の継承に前向きな回答が6割を占めた。

日本のお墓を明るく美しくしたい
陶器製品を中心に、インテリア・エクステリア・バラエティ雑貨などの企画・製作を手がけるセトクラフトが、なぜ陶器製のお供え花を開発することをめざしたのか。
きっかけは、2023年夏、代表取締役会長・鈴木幸世さんが、フランス・パリ近郊にあるオーヴェル=シュル=オワーズという街に画家ゴッホ(フィンセント・ファン・ゴッホ)の眠る墓地を訪れたこと。墓地内に手向けられた色とりどりの花々が美しく、輝いて見えた。そして、実はそれらが自らの事業でもある「陶器」で作られていたことに驚いたからだという。
セトクラフト 鈴木幸世 代表取締役会長
「その時、ふと日本のお墓を思い起こしまして。うす暗くて寂しいイメージのある日本のお墓をこんなふうに明るくしたいな、と。陶器の花なら太陽が当たっても色褪せない。雨に当たっても、埃や泥がついても水洗いで簡単に綺麗になる。陶器のお花なら、いつまでも変わらず美しい。うちの会社で作ってみたい。そう思ったんです」
もともとセトクラフトは、「世の中にないものを作る」をテーマに、陶器のインテリア製品をはじめ、エクステリア、さらにはキャラクターまで陶器の領域を超えて様々な分野の製品をオリジナル開発してきた会社だ。鈴木会長は、世の中にない陶器製のお供え花を製作するため、フランスから帰国するや否や、社内のデザイナーと試作品づくりを開始した。

細部にこだわり、デザイン性を追求
花RENNU(カレンヌ)と命名された陶器製の花の開発で最も重視したのは、華やかなデザイン性を追究することだった。それが花立てに置かれているだけで、お墓全体が明るく、美しく見えるようにするために、花の魅力を引き出し、花の咲き方、花びらの質感、時には鮮やかな色合いとカラーグラデーションを用いながら、カレンヌならではの造形美をカタチにしていく。表面は、素焼きの陶器にガラス釉薬(うわぐすり)を全体にかけて焼く製法を施し、光沢や味わいを表現。ガラス釉薬はコーティングの役割も担うため、焼き締まることで硬さが増すとともに、より割れにくく、より汚れが付きにくくなる効果を発揮する。
また、お墓参りで花を供える時は左右対称になるように飾るため、同じ組み合わせの花を左右対称の型でそれぞれ製作し、一対になるように製品を作っている。細かなところまで手を抜かずこだわることからも、カレンヌにかける思いの強さがにじみ出ていた。


遠方からのお墓参りを手軽に楽しく
屋外のお墓に供されるのは、生花か、最近よく見かける造花が多い。陶器製のお供え花を見かけることはない。しかし、鈴木会長がフランスの墓地で思ったように、陶器はお墓にこそふさわしい特性をいくつか併せ持っていた。カレンヌというネーミングにも託されているように、陶器のお花は「可憐さ」とともに「枯れない」という特長がある。枯れないということは、お墓参りの後でゴミが出ないということだ。
生花の場合、お墓参りを終えた後から徐々に枯れていき、見栄えが悪くなっていく。 それだけでなく、花立ての水が腐食し、臭いや虫を発生させてしまい、墓地全体に悪影響を与えてしまう可能性もある。陶器の花ならそんな心配は無用。
カレンヌは、強さと美しさを兼ね備えたニューボーン(磁器)製のため、色褪せがほとんどなく、太陽光や風雨にさらされてもほとんど劣化しない。軽く水洗いをするだけで、さっと汚れを落とせて綺麗になる。これなら、遠方からのお墓参りも少しは手軽にできそうだ。


お墓参りの伝統文化を子供たちに伝えたい
日本人にとってお墓は、故人を思い起こし、ご先祖様や家族とのつながりを再認識する大切な場所である。時には故人に悩みを打ち明けたりすることも。お盆やお彼岸、命日などに家族・親族が集まれば、絆を確認したり、一緒に食事をしたり、楽しい時間を過ごすことができる。
しかし近年、「お墓離れ」が進み、お墓参りに出かける回数が以前より少なくなり、それに合わせて子供を連れていく機会も減っているのではないだろうか。
セトクラフト 掛布敏章 代表取締役社長 「子供が親に連れられてお墓参りに行ったときに、寂しい場所で少し怖かったという印象を持ってしまうと、もう行きたくないとなってしまう。『いつ行っても花が綺麗で可愛い』となると、『また行きたいね』という気持ちが芽生えてくる。そんなことを願ってカレンヌを発売した経緯もあるのです。だから、お墓を子供たちにとって楽しい場所、行きたい場所に変えていきたいのです」
実は、幼いころからのお墓参りの体験が、子供の情操教育に大きな影響を与えると言われていることをご存じだろうか。とくに、親が先祖を敬う姿勢を子供たちに見せることが情操教育に非常に大きな役割を果たすという。一般社団法人 全国優良石材店の会が行った調査によると、お墓参りの頻度が高い子は、命を大切にする気持ちを育むという結果報告があった。(※注)
お墓参りの回数が多ければ多いほど、その傾向が顕著になるようだ。
昨今の墓じまいは、子供に負担をかけたくないと親が計画するケースが多いが、むしろ子供は墓を継ぐことを負担に思っていないようだ。お墓参りは家族の大切な機会であることを考えると、「子供のために」と安易にお墓を手放してしまうことはむしろ逆効果になるのではないだろうか。
※全国の石材店約300社で組織される墓石業の専門店グループ「一般社団法人 全国優良石材店の会」が15歳から29歳までの全国の男女1000名を対象に「お墓」および「お墓参り」が子供の情操教育に与える影響を確認する目的でアンケート調査を実施。(2017年5月)
「小学校低学年に月1回以上墓参りに行っていた」人の約8割が「他の人の命も大切だと思う」と回答。
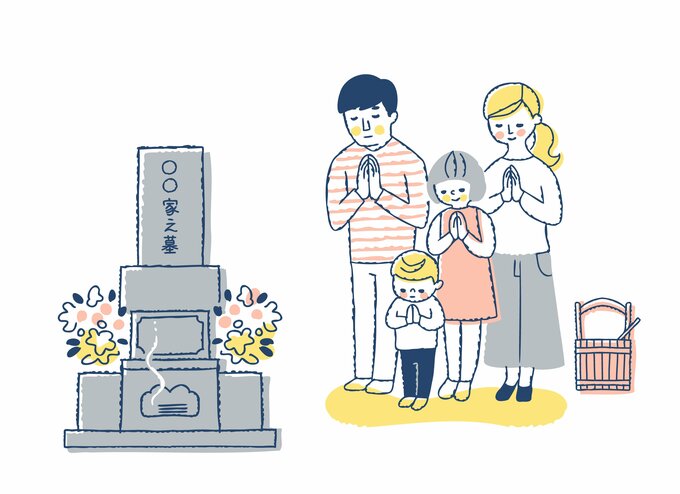
時代の流れに合わせた変化も必要
カレンヌの商品化は着々と進んだが、気がかりな点もあった。宗教の教えや伝統を大切にする方などから「陶器製の墓花は好ましくない」と見られないかという点である。その可能性について寺院や墓石の専門家に確認をとっていた。
住職は「宗派などによって、お墓に供するのは『生花でなければならない』『花の種類はこうでなくてはならない』という教えもありますが、時代の流れもあり、選択肢の一つとして陶器製のお花があっていいと考えています。『カレンヌ』は非常に綺麗で、お手入れも簡単なので、今この時代に合ったお供え花だと言えると思います」と語った。
墓石を扱う石材店の社長からは「お墓参りに行く回数が減った人の中には、生花や造花の手入れの大変さもあると伺っています。その点でみれば、『カレンヌ』を用いることでお墓に行く頻度が増え、簡単に墓じまいをすることもなくなるのではないでしょうか」との回答があった。
もちろん「好ましくない」という反対意見もあったが、全体から見れば好意的な声が大半を占めていた。印象的だったのは、「宗教上の制約や伝統に縛られてお墓に行かなくなるよりも、お墓の前で手を合わせることを大切にしたい」という一般の方々の声だった。日本の伝統文化でもあるお墓参りを継承していくためには、時代に合わせて変わっていくことも必要なのかもしれない。
生花や造花も含めたハイブリッド方式も
代表取締役社長・掛布敏章さんは「ガソリンと電気、それぞれの利点を組み合わせるハイブリッド車の発想を活かせば、お墓参りはより持続可能なものとなる」と提案する。
その一つが、お墓参りでは生花をお供えし、帰る際に生花の代わりにカレンヌを花立てに挿して、生花は自宅に持ち帰り飾るという新たなスタイル。この方法なら、次のお墓参りまでお寺のゴミにはならず、生花も有効活用できる。
掛布敏章 代表取締役社長
「個々のライフスタイルや周期のタイミング、季節などの条件に合わせて柔軟に使い分けていただくと、周囲からの印象もよくなり、よりお墓が明るく、行きたくなる場所になるのではないでしょうか」

お墓まわりを我が家流にトータルコーディネート
発売したばかりの「カレンヌ」は、これから本格的に商品のラインアップを充実させていくという。花のバリエーション展開はすでに発売間近の段階に。供花だけでなく、「花台」や「線香立て」、「ろうそく立て」といった墓前の用具の商品化も進行中だ。花台は、仏教式、キリスト教式、神道式を、というように。線香立て、ろうそく立ては、風で火が消えないようにする工夫も。
お墓はいわば故人と家族の家のようなもの。掛布社長はわが家のお墓らしくトータルコーディネートを楽しんでもらえる商品を多彩に取り揃えていくという展望を示していた。

セトクラフト株式会社:カレンヌの詳細はこちら
